 |
 |
 |
 |
| 春の養蚕 |
| ●2009年6月22日 春の養蚕報告11 ― |
| 6月14日農協に出荷された松井さんの繭は、安中市松井田町の碓氷製糸に運ばれました。松井さんをはじめ4戸の絹の会が特約飼育をお願いした農家の繭は計930キロ、赤いリボンで印をして区別されます。碓氷製糸では、翌日の15日から3日間をかけて生繰りされました。今年出荷された繭では初めての繰糸が、絹の会の生繰りとの事です。最高品質の生糸を作るためには3つの条件があるといわれています。3つの条件とは、①最高品質の繭を、②最高の製糸技術で、③生挽で低速繰糸することです。 ○最高品質の繭とは:解じょ率(繭糸のほぐれ歩合)が85%以上で、選除繭が0.3%以下生糸の品質は、繭品質80%、繰糸技術 20%といわれていますので、繭の良し悪しは生糸品質に大きく影響します。 ○最高の製糸技術とは:繊度ムラが少なく、節の少ない生糸を作る技術 ○生挽きで低速繰糸とは:生挽きの生糸は、繭を乾燥処理しないため(タンパク質が変性しないため)、光沢、伸度、風合がよい 製糸は次のような工程で行なわれます。 |
| ○選繭・毛羽取り・・・・・・ | 最高品質の生糸を作るために、玉繭、外部汚染繭、内部汚染繭、奇形繭などを除去します。 |
| ○煮繭・・・・・・・・・・・・・・ | 繭糸がよくほぐれるように繭を煮ます。 |
| ○繰糸・・・・・・・・・・・・・・ |
風合いの良い生糸を作るために100~110m/分の低速で繰糸します。生糸繊度は21中です。(生糸は天然繊維のため多少の繊度ムラがあります。そのため、「中」という言い方をします) |
| ○揚げ返し・・・・・・・・・・・ | 小枠の生糸を乾燥させながら大枠に巻き返すことを揚げ返しといいます。これも生糸の風合いを良くするために低速で行います。また、節の少ない生糸を作るために、スラブキャチャーで節取りを行います。 |
| ○括作り・・・・・・・・・・・・ | ねじ作りした生糸の綛(かせ:1綛 約250g)を4綛並べ5段重ねにして束ねます。これを括(かつ)といいます。1括は約5㎏です。 |
| ○出荷・・・・・・・・・・・・・・ | 6括(約30kg)をダンボール箱で梱包して出荷されます。 |
 |
 |
 |
 |
| ●2009年6月12日 春の養蚕報告10 ― 毛羽取り ― |
|
34日前、目で確認するのも難しいほどの小さな黒い毛蚕が、真っ白い立派な繭を作り上げました。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
| ●2009年6月6日 春の養蚕報告9 ― 営繭 ― |
| 昨夜、松井さんは深夜2時に目が覚め、見回ってからほとんど寝ていないのだそうです。「蚕の小便の始末に時間がかかってさ」蚕は繭を作る準備が出来ると一度だけ、一生分の大量のおしっこをします。下の受けにたまる仕組みのおしっこを、丹念に始末しているからなのでしょう、蚕室は何の臭いもしません。気温23℃、湿度70%に保つ為に、大きなボイラーによる暖房と除湿機3台、換気扇8台がまわり続けます。室内はすがすがしく快適な状態です。人間にとって気持ちのよい環境は、蚕にとっても快適なのでしょう。休むことなく蚕は、2昼夜をかけ繭を作り上げます。このときにいかに気持ちよく糸を吐かせるかが腕の見せ所なのです。 すでに族の枠に入り営繭をはじめる蚕もいれば、まだ自身の納まる場所を求めて動き回る蚕もいます。昨夜から松井さんは、おしっこの処理、温度湿度の管理だけでなく、回転族を時々廻す作業を繰り返していたのです。上に上る習性の蚕を回転させる事によって、行き場に導いてやるのです。4日5日とほとんど睡眠も取れない松井さん「今が給金場だからやるっきゃないやね。」と言います。蚕がそれぞれの枠に収まり糸を吐き終えるまで、気の抜けない日々です。 |
|
 |
 |
 |
 |
| ●2009年6月4日 春の養蚕報告8 ― 上族 ― |
| 蚕はおいしい桑を腹一杯食べました。足は半透明のアメ色となり、糸を吐く準備が完了しました。この時期の蚕を「熟蚕」といいます。群馬では「ズウ」とか「ズー」といいます。当初6月5日の予定だった上蔟の作業は、1日早い4日午前9時からとなりました。この上蔟のタイミングを計ることが難しく、蚕の経過と永年の経験から判断するようです。「蚕飼いは60回飼って一人前」といわれますが、松井さんは中学生の時から養蚕に携わったといいますから、かれこれ45年以上にもなります。上蔟とは繭を作らせる為に、蔟(まぶし)に入れること、いよいよ養蚕は最終段階となります。いつもは、ご夫婦お2人での作業ですが、今日は6人ものお手伝いの方が来ています。お話の様子から、ご親戚の方のようです。毎回手伝いをされているとみえ、それぞれの役割分担が決められている様子です。作業はまず、桑の枝で高く層を成した蚕座に網をかぶせ桑を与えます。時間がたつと蚕はその網の上に上ってきます。蚕には上に上にと上る習性があるのです。そこでまとめた蚕と、桑の枝に付いている蚕をふるい落とす機械(条払い機)により集めた蚕が、再び網の上にまとめられます。 | |
 |
 |
 |
 |
| それを2階の上蔟のための部屋に持ち上げます。計量器で約600グラムおよそ120頭の蚕を蔟の上に移します。この蔟一枚には、156の枠があるそうです。それぞれの蚕がマスに入り自分の巣を作る事が不思議です。 | |
 |
 |
|
この回転蔟を天井から3段に吊るします。回転蔟は、昭和30年代に開発されたものだそうですが、簡単な道具でありながら蚕の習性を生かし、大変うまく作られています。しかしこの蔟も、もうすでに生産が中止されているとの事です。このようなところにも、養蚕の危機を感じます。 |
|
 |
 |
| ここまでの作業を終えたのが午後5時半、半日だけのお手伝いでしたのに、腰に疲れが残る作業でした。これから2日間、蚕がいかに気持ちよく糸を吐けるか、松井さんの技術と経験の見せ場です。 |  休憩中の松井さん(右肩に蚕が・・・・・) |
| ●2009年5月30日 春の養蚕報告7 ― 猛烈な食欲の日々 ― |
|
一昨日と違いがわかるほど、蚕は成長しています。松井喬さんの蚕室前は、刈り取った桑が山のようです。しばらくは、玄関からも出入りできません。今、蚕は日ごと、時間ごとに成長しています。松井さんは、昔ながらの蚕箔という竹篭で蚕を飼っています。その為に籠の上に次から次へと与える桑の枝で、そこではもうすでに50cmくらいの層が出来ています。さらにその上に新たな桑を与える作業は、日ごとに過酷なものとなります。朝5時に、前日夕方採った桑を与えます。朝は蚕が一番お腹を空かせている時、大きな音を立てて桑を食べます。朝食後再び桑採りに、11時に再び与え、昼食後午後7時に与える分と朝与える分と、大量の桑を採る為に桑園との間を何往復もします。蚕の成長と、桑採りと競争の毎日です。 |
|
 |
 |
 |
|
| ●2009年5月28日 春の養蚕報告6 ― 庭休み後― |
| 最後の眠(庭休み)を終えた蚕は、これまでに増して旺盛な食欲を見せています。耳を澄ますと、さわさわと桑を食む音が雨が降っているようだと形容されます。絶え間なく桑を食べる蚕は、これから5日間さらに大きく成長します。 | |
 |
 |
| ●2009年5月26日 春の養蚕報告5 ― 庭休み前― |
|
5月24日、蚕はもう、4~5センチ位の大きさ、目覚しい成長です。今は「庭休み(4眠)」前、もう1日で、最後の眠に入ります。今でも蚕室いっぱいに広がる蚕座ですが、やがて2段になり、作業する空間もだんだん狭められてきます。5令になると、午前5時・11時そして午後7時の給桑、その間をぬっての桑採りと連日息をつく間もないほどの忙しい日々が続きます。 |
|
 眠の蚕(頭をもたげて休んでいます) |
 |
 |
 |
| 「蚕の一生」について解説したいと思います。 蚕は、完全変態の昆虫です。鱗翔目カイコガ科に属し、和名で「カイコガ」といいます。蚕の一生は約45日です。 |
|
| ○幼虫の時代・・・・ | 蟻蚕は、卵殻をかみ破って出てきます。蟻蚕の体長は約3mm、体重は100頭で45mgくらいです。約4週間の間に4回眠り、4回脱皮して熟蚕となり繭を作り始めます。 |
| ○蛹の時代・・・・・・ | 糸を吐き始めてから2~3日で繭が完成します。繭は、雨も風も通さず、中の蛹を守るためのシェルターの役目をしています。 繭が完成してから2~3日で繭中で脱皮して蛹になります。蛹の期間は12日ほどで、脱皮して蛾になります。 |
| ○蛾の時代・・・・・・ | 蛾は口からアルカリ性の液を出し、繭層を柔らかくして外へ出てきます。朝早くに繭から出て、その日のうちに交尾して、夕方から翌朝にかけて産卵します。その後は次第に体力が衰え、4~5日後に死にます。 |
| ○卵の時代・・・・・・ | 産卵数は、1蛾で500~700粒の卵を産みます。自然状態で年1世代の蚕を「一化性」、2世代のものを「二化性」、3世代以上繰り返す蚕を「多化性」といい、一般に飼育されている蚕は、一化性または二化性です。 |
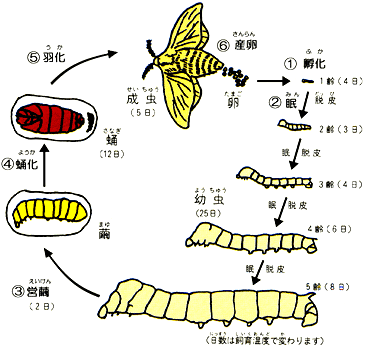 |
|
| ●2009年5月25日 春の養蚕番外編 (こぼれ話2) ―金色姫伝説― |
| 松井喬さん宅の蚕は3眠中。石灰をかぶり、頭をもたげて静かに休んでいます。フラッシュ撮影すると、蚕が驚きそうなので、写真はアップしません。 さて、蚕は4回休みます。農家は、初眠のことを「シジ(獅子)休み」、二眠のことを「竹(鷹)休み」、三眠のことを「船休み」、四眠のことを「庭休み」といいます。 なぜそのように言うのか、「金色姫伝説」から見てみましょう。 昔、雄略天皇の時代に、天竺に旧仲国という国がありました。帝はリンエ大王といい、金色姫という姫がいました。皇后が亡くなり、後添の皇后を迎えましたが、この皇后はとても意地の悪い人で、金色姫のことを憎みました。 皇后は大王の留守に、金色姫を家来に命じて、獣の多い山へ捨てさせました。しかし、獣は姫を拝み、一匹の獅子の背に乗って、姫は御殿に帰ることができました。 皇后は、ますます姫を憎み、次は、鷹群山という、鷹や鷲のたくさんいる山へ捨てさせました。ちょうどその頃、帝が兵士に鷹を撃たせにやりました。兵士は山中に姫がいるのに驚き、姫を連れて御殿に戻りました。 皇后は、今度は姫を海眼山という草木のない島へ流しましたが、今度も姫は、漂着した釣船に助けられました。 腹を立てた皇后は、大王の留守に、城の庭に七尺の深さの穴を掘らせ、無残にも姫を生き埋めにしました。 ある日、庭から、光がさして城を照らしました。大王が不思議に思って、そこを掘らせると、地中に金色姫がいました。大王は、すっかりやつれた金色姫を哀れに思い、桑の木のうつぼ舟をつくって、泣く泣く姫を舟に乗せ、海上はるかに舟を流しました。 舟は荒波にゆられ、風に吹かれ、流れ流れて、茨城県筑波の豊浦に漂着しました。ここに、権太夫という漁師がいて、舟を引き上げると、なかに優しい姫が一人いました。権太夫は、家に連れ帰って、姫から一部始終を聞きました。権太夫夫婦はいっそう哀れに思って大事にしましたが、姫はふと病の床についたかと思うと、間もなく亡くなってしまいました。 夫婦は嘆いて、清らかな唐びつを作って、姫のなきがらを納めて大切にしていました。するとある夜、夢の中で「私に食物をください、後で必ず恩返しをします」と姫がいいます。唐びつを開けてみると、姫のなきがらは水に溶けて、たくさんの小さな虫になっていました。夫婦は姫への食物として、丸木舟が桑の木であったことから、桑の葉をとって虫に与えると、虫は喜んでこれを食べ、成長しました。 |
| ある時、この虫たちが桑の葉を食べず、皆一様に頭をあげてワナワナとしています。権太夫夫婦が心配していると、姫が夢にあらわれて、「心配しないで下さい。私が天竺にいた時、継母に獅子の山に捨てられ死にかけたり(しじ休み)、鷹の山に捨てられ死にかけたり(たけ(鷹)休み)、草木もない島に船でながされ死にかけたり(船休み)、庭に埋められ死にかけたり(庭休み)、苦しみの耐え難さに、今休んでいるのです」といいました。最後の「庭休み」のあと、マユをつくりました。この虫はクワの葉を食べ、姫が死にかけたのと同じ回数だけ死んだように眠り、繭を作りました。これが今でいう蚕です。マユができると、筑波山の神様が現われて、マユから糸をとることを教えました。ここから、日本で養蚕が始まりました。権太夫は、ますますこの業を営んで栄え、豊浦の船つき河岸に新しく御殿をたて、姫の御魂を、左右に富士、筑波の神をまつって、蚕影山大権現と称号しました。これが蚕影山神社の始まりです。 |  蚕影神社 |
| ●2009年5月21日 春の養蚕番外編 (こぼれ話1) ―蚕の先祖― |
| 朝6時、庭に一本植えてある枝垂れ桑にカイコのご先祖様である「クワコ(桑蚕)」を見つけました。体長4cmくらいの5令幼虫です。 カイコは、繭から絹糸をとるために人が飼育している虫です。今から5000年以上も昔の中国で、「クワコ」という野蚕を飼い慣らし、その後もずっと品種改良を重ねて作り上げたのがカイコです。カイコはほとんど移動しません。蚕の餌である桑が無くなっても与えられるまで待っています。成虫(蛾)は、羽があっても退化していて飛ぶことが出来ません。つまり、カイコは人が面倒を見てやらないと生きてゆくことが出来ないのです。 ではなぜ「カイコ」と呼ばれるようになったのでしょうか。古い時代には、カイコは蚕(こ)と呼ばれていました。人が蚕を飼うようになったので「カウコ」から「カイコ」になったとも言われていますし、神様が蚕(こ)を生んだので、「カミコ」から「カイコ」と呼ばれるようになったとも言われています。 |
 |
| ●2009年5月18日 春の養蚕報告4 ― 配蚕― |
| 午後2時、3令3日目の蚕100箱を 33軒の農家に配る「配蚕作業」が始まりました。掃き立て時に比べ、体重が500倍以上になり健康そのものの蚕、これからは養蚕農家で大好物の桑を腹一杯食べ、白く大きな繭作りに専念することになります。 では、配蚕作業を写真で紹介しましょう。 |
|
 |
蚕を蚕座紙と防乾紙で包み、コンテナに入れます。昔は、蚕座紙に包んだだけで農家に配蚕されましたが、人工飼料育では配蚕時に蚕を痛めないよう細心の注意を払い、コンテナに入れて配蚕しています。 |
 |
コンテナに入れられた蚕は、トラックに積まれ各農家に配られます。大胡飼育所の掃き立て量は100箱、配蚕戸数は33戸なので、1戸平均3箱が配蚕されていきます。 |
 |
 |
 |
松井喬さんの蚕室に運ばれた蚕は5箱、コンテナから取り出された蚕を、蚕座紙いっぱいに広げ、網を掛けて、桑を与えます。 稚蚕共同飼育所では、蚕の成育が揃うように温湿度管理や作業を行っていますが、1箱には30,000頭いますので、蚕の経過もそれぞれです。そこで、網を掛けて生育の遅い蚕と生育の早い蚕を分けて、経過を揃えます。 飼育経過を揃えることは、よい繭を作るためには欠かせない作業です。 |
| ●2009年5月17日 春の養蚕報告3 ― 3令餉食(2日目) ― |
| 5日間振りの蚕は、見違えるほどの成長を見せていました。 今日は3令の2日目、この間2回目の眠、そして脱皮を繰り返して、体長はおよそ2.5cmくらいに、形状もすっかり蚕の姿です。掃き立ての時、B4大の紙に15000頭もの毛蚕がいるといわれても、到底信じられませんでしたが、今ではそれが蚕座いっぱいにまで広がり、確かにその数が存在しているのだと実感できます。 5月8日・12日にご報告した蚕座の様子と、比較してみてください。明日18日は、いよいよ配蚕の日です。共同飼育稚蚕センターで飼われた蚕が、それぞれの農家に引取られて行きます。 そして明日から蚕は、人工飼料でなく、新鮮な桑の葉を与えられ育ちます。人工飼料は、桑の葉の粉末に大豆粕などが加えられたものですが、これを与えられ3令まで育った蚕でも、一度桑の葉を食べてしまうと二度と人工飼料は食べません。鮮やかな緑の桑の葉と比べいかにも食欲をそそりそうもない飼料だからでしょうか。熟蚕になるまで蚕が食べる割合では、人工飼料で生育するのはわずか5%との事、95%は桑の葉で育ちます。この大胡町共同稚蚕飼育センターで育てられた蚕は、17戸の大胡町の養蚕農家と、一部は前橋の他の地区の農家にも配られて行きます。 11日間、蚕を見守り続けたJA前橋の楠由輝夫さんも、明日はやっと自宅に戻れる日です。 |
|
 |
 |
 |
 |
| ●2009年5月12日 春の養蚕報告2 ― 2令餉食(桑付け) ― |
|
孵化・掃き立てから4日目、今日は体重が掃き立て時の約15倍になり、脱皮を終え、お腹をすかせた2令の蚕(2令起蚕)に人工飼料を与える作業、「桑付け」作業です。桑付け作業の時期を決めるのは、養蚕技術者の腕の見せどころです。休んでいる蚕が多いうちに桑付けると蚕が不揃いになるし、遅すぎると蚕の健康を害してしまいます。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 養蚕技術者が最も神経を使うのが桑付けの時期です。写真億のJA前橋大胡支所の指導員、楠由輝夫さんは、掃き立ての前日から「配蚕」の18日まで飼育所に泊り込み、昼夜を分かたず蚕を見守り続けます。 | |
| ●2009年5月8日 春の養蚕報告1 ― 掃き立て ― |
| 午前7時、前橋大胡町之共同稚蚕飼育センターで、平成21年度春繭の掃き立て作業が行われました。いよいよ今年の養蚕のはじまりです。6時40分蚕の種屋さんから「群馬200」の毛蚕が届けられます。B4大の台紙に卵から孵化したばかりのかえった幼虫、約15000頭が黒い芥子粒のようにびっしりと取り付いています。目を凝らすとわずかに動くのが確認できます。蚕の幼虫は卵を破って出た時約3mm、小さな体が蟻のように見えることから蟻蚕(ぎさん)、毛蚕(けご)とも呼ばれます。この蟻蚕を羽箒で静かに飼育の場に移す事からこの作業を「掃き立て」というのだそうです。現在では、蟻蚕の上に人工飼料を落としての作業となります。 この作業場には3つもの部屋を通りそれぞれ手・足・履物を消毒、白衣に着替え、帽子をかぶり、マスクを着用して入ります。かれから蚕は10日間、室温30℃、湿度90%という環境におかれます。 かつて養蚕は、病気の蔓延など非常にリスクの高い仕事でした。身を清め神仏に祈願して蚕室に入ったといいます。 「神棚の灯は怠らじ蚕時」と蕪村の句にあるように、神仏の力を仰いでの作業でした。 今日このように蚕室や作業員の殺菌を十分に行い、その作業に当たるため大きな失敗はありません。でも全てに「怠らじ」の心が生きていることを感じました。 この飼育場で3齢まで育てられた蚕は、大胡町の養蚕農家16戸と近隣の地区の農家に5月18日に配送されます。 |
|
 のり付台紙(1枚に15000頭) |
 毛蚕 |
 作業をする松井喬さん |
 毛蚕の上に羊羹のような人工飼料 |